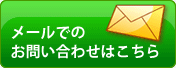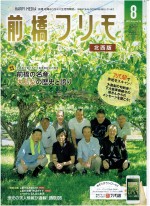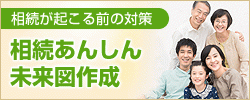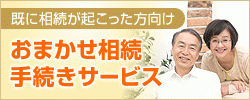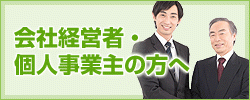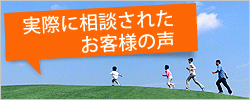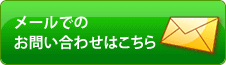相続対策に超便利!生命保険が持つ2つのメリットとその理由
私が生命保険会社へ勤めてまだ間もない頃、とても悔しい経験をしたことがあります。
あるお客様からのご紹介でお会いした、金融機関にお勤めの30歳の独身女性。
とても家族思いで、人生設計についてもしっかりと向き合う方でした。
「まだ生命保険に加入したことがない」とのことなので、保障への考え方や生命保険の仕組みなどについてお話をさせていただきました。
そして生命保険の必要性を感じていただき、後日あらためて保障プランを設計・提案をすることになりました。
提案内容は、お客様の将来への考え方を反映させたものだったので、とても気に入って頂くことができました。
ですので加入意思があると思い手続きについて促しましたところ、
「このプランでいつか加入をします。」
と思いもよらない返事が返ってきました。
きっと私に至らないところがあったのだけれど、それを言いにくかったので断られたんだな、
と真摯に反省し、その日はお別れしました。
そして約一年後のある日、その方から私の携帯電話に連絡がありました。
「以前提案してもらった生命保険プランに加入をしたい」
とのこと。
前回お会いしたファストフード店で待ち合わせ、もう一度提案内容をご説明差し上げました。
すると内容に満足して頂いたので、そのままご加入手続きへ入りました。
その手続きの中には、最近医師の検診を受けたか、健康診断で再検査や要精密検査の項目はなかったか、など直近の健康状態を問う「健康告知」があります。
「正直に答えなければいけませんか?」
と聞くお客様。
「はい、ありのままお答えをいただけないと告知義務違反となり、保険会社は一方的に契約解除をする権利がありますし、保険金もお支払いができなくなります」
と私。
「わかりました」とお答えの後、次の項目の質問へ「はい」に○を付けました。
「いままでにがんにかかったことはありますか?」
詳しくお聞きすると、
「今年会社で受けた健康診断の結果に、要精密検査項目があった。再検査を受診すると、卵巣に悪性腫瘍が見つかり、がんと診断された。これはいけないと思い、生命保険に加入をしようと思ったのです。」
お客様のお気持ちを汲み取り、生命保険の加入条件について丁寧にご説明をしました。
端的に言うと、謝絶(生命保険の引き受けができない)となります。
生命保険は相互扶助の考えに基づいているので、加入者間の公平性を保つために、一定以上の健康状態の方じゃないと引き受けができません。
残念ながら、そのお客様のお引き受けはできませんでした。
とても悲しそうに肩を落としてお別れしたことを、いまでも覚えています。
なぜ最初に会った時に、「いつかは誰でも加入条件を失う」ということをきちんとお伝えしなかったのか。
そうしていれば、このお客様は無保険という不安から解放され、経済的には安心をして病気と向き合うことができたのじゃないか?
とても後悔と反省をしました。
その経験を経た後は、「加入条件の期限」について毎回お伝えをしていきました。
加入の意思はお客様に委ねられますが、加入条件の期限を伝えることは、生命保険募集人の責務だと捉えているからです。
では、なぜみんな生命保険に加入をするのでしょう?
なんで生命保険に入るの?
日本人のほとんどが加入している生命保険。
いつも私は、
「何のために生命保険に加入をしているのですか?」
と、お会いする人に必ずお聞きします。
すると、
「何かあった時に困るから」
と多くの方がお答えになります。
「それはどんな事柄に対して、どれくらい困るのですか?」
とお聞きすると、明確な答えを返してくれる方はあまりいません。
人それぞれ目的や家族環境、想いが違いますから、答えは多種多様になります。
子育て世代なら、残される家族への生活費や教育費。
シニア世代なら、葬儀費用や医療費など。
会社経営者なら、事業への借入金をカバーする目的もあるでしょう。
しかし忘れられがちなのは、相続対策費用。
残される家族が円満に過ごしていくために必要な費用なのです。
相続対策としての生命保険金の使い方
相続対策費用で代表的なものは、相続税の納税資金です。
ある一定以上の遺産がある場合は、遺族に納税の義務が発生します。
その遺産のほとんどが換金できないものだったとしたら…。
これからも住み続けていく家、経営する会社の自社株や貸付金、他人へ貸している土地など。
税金は納めなければならないが、現金がない。
このようなときに生命保険が有効に活用できます。
また特定の人に遺産を集中させなければならないとき。
経営する会社の財産すべてを後継者の長男へ、家と土地は妻へ相続するとした場合、他の相続人は不満に思うことでしょう。
その不満を解消するために、他の相続人には生命保険金を分けてあげられるように加入をすれば、円満に遺産分割ができます。
また生命保険ならではのメリットがいくつかあります。
生命保険金の支払いは迅速かつ確実
「相続」と「生命保険」の親和性はとてもいいです。
なぜなら、確実に保険金受取人へお金が渡せるからです。
「この人に万が一のことがあったら、この人にお金を遺す」
という契約は確実に履行されます。
しかも、数日以内に入金がされます。
銀行などに預けている預貯金は、相続人全員の同意がないとお金をおろすことや解約ができません(一部、葬儀費用支払いへのものを除く)。
また不動産と違って分けやすい財産なので、遺産分割対策にとても有効です。
そして相続税の納税資金としても使えるので、納税資金対策にもとても有効です。
保険金は受取人固有財産
もうひとつ大きなメリットは、生命保険金は「受取人固有の財産」であることです。
どういうことかと言うと、この生命保険契約については「なんぴとたりとも手を付けることができない」ということ。
例えば、
Aさんは預貯金や土地建物などのプラスの財産よりも、借金などのマイナス財産の方が多いとします。
Aさんが亡くなったら相続人(財産を引き継ぐ人)は借金を引き継ぐことになるので、それを避けるために相続放棄(財産のすべてを放棄すること)をするとします。
ではAさんは、何ひとつ財産を遺すことはできないのか?
しかし生命保険金は受取人固有財産なので民法上相続財産に含めない、という特徴があります。
この特性を利用し、「事前に生命保険に加入しておいて、相続人は相続放棄をし、保険金を残す」という方法も考えられます。
実際に私のお客様で、億単位の借金によりご家族は相続放棄をしましたが、数千万円の保険金をお届けし手元に残して差し上げた経験があります。
いかなる債権者(借金取り)も、この保険金には手を付けることはできませんし、相続放棄をしている以上は返済する必要もありません。
この事実を知っているのと知らないのとでは、遺せる財産に大きな差が出てしまいます。
ぜひ覚えておいてください。
節税効果は副産物
よく見聞きする生命保険による相続対策の多くは、節税効果をうたったものがとても多いです。
それは人には「得をするよりも損をしたくない」という損失回避性が備わっているので、その心理をくすぐったセールス手法に則ったものだからです。
中には、節税こそが相続対策の本丸!というニュアンスの情報もあったりします。
しかし生命保険の本質は、「約束された保障額を、約束した人に支払い、受け取った人の経済的な困窮を防ぐこと」だと私は考えます。
ここを忘れてはいけません。
あくまで節税効果は副産物であり、二次的効果です。
節税ありき、で本質を見誤ってはいけません。
目的をきちんと考えて加入しましょう。
プロフェッショナルから加入しましょう
私は長い間にわたって生命保険を取り扱ってきたので、その有用性や利便性など生命保険が持つ機能の素晴らしさをよく知っています。
様々な場面で、いろんな使い方ができる金融商品です。
しかしそれも、使い方を知っているかどうかが肝になります。
賛否あることを承知で言うと、ちょっと生命保険を見聞きかじったことのある専門家の意見や、素人が判断してインターネットで加入することに対して、私は否定派です。
せっかくの使える機能を知らぬまま、見過ごしてしまうことになるからです。
加入の際には、「生命保険に精通している担当者から」をオススメします。
そして繰り返しになりますが、人はいつか必ず加入資格を失います。
それがいつ訪れるかは、誰にも分かりません。
それを踏まえた上で、自分の保険は現在の自身の置かれた状況にあっているのかチェックをしてみましょう。
気になる方はチェックのお手伝いもできますので、どうぞお問い合わせを下さい。