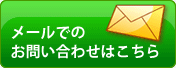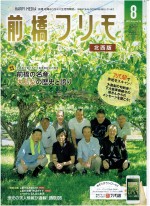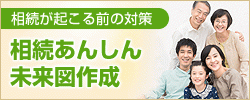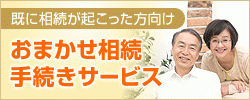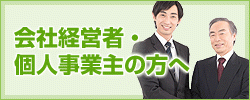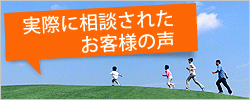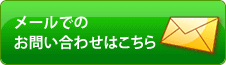なぜ揉めやすい?二次相続
我が家には二人の中学生がいます。
育ち盛りなので、夕方から「腹減ったー」といつも騒いでいます。
ようやくありついた夕飯の食卓、並べられたおかずを我先にと箸をつける子供たち。
大皿料理ならそうでもないのですが、餃子やから揚げなど、数えられるようなおかずだとその分け方で小競り合いが発生します。
「何個食べた?」
「そっちは何個食べた?」
「ずるーい!」
「ずるくねーよ!」
などと、つまらぬ揉め事が絶えません。
から揚げ1個の分け方のせいで、時には人格否定みたいな言葉まで飛び交うこともあります。
矛を収めさせる役は、いつも私。
私の分をあげて数を均等にしたり、しかるべき理由を言って納得をさせます。
そして争いは収まり、何事もなかったかのようにいつもの兄弟関係に戻ります。
やれやれ。
しかし相続争いだと、こうはいきません。
なぜでしょう?
その理由をお伝えしますね。
仲裁役がいない
私のところへ相談にいらっしゃる方は残念ながら、すでに揉めている、あるいは不満たっぷりで揉める寸前、の方が多いです。
その中でも多いのが、二次相続をきっかけとしたことです。
二次相続って何のこと?
一次相続とは、両親のどちらかが亡くなって、配偶者と子供で相続をすることです。
二次相続とは、さらにもう一方の親が亡くなって子供だけが相続をすることです。
揉め事になるきっかけはどちらにもあるのですが、二次相続の方が争いが長引く傾向が強いです。
なぜかと言うと、仲裁役がいないから。
一次相続の場合、親の財産を引き継ぐのはその配偶者、という意識があるからだと思います。
父が亡くなったら母、または母が亡くなったら父が引き継げばいい、というものです。
それまで長い間に渡って共に築き上げてきた財産ですから、子供たちからも納得をしやすいでしょう。
そしてもし子供たちが遺産の事で揉めたとしても、親が仲裁役となってそれを収めてくれます。
しかし、二次相続は違います。
親が遺した財産を、子供たちで分け合います。
そして残念ながら揉めてしまった場合は、その矛を収める仲裁役がいません。
から揚げ1個の争いとは、話が違います。
お互いの主張がぶつかり合い、相続とはまったく関係のない昔の出来事なども掘り返されて揉めたりします。
中には仲裁役として弁護士を依頼される方もいらっしゃいますが、その選択をすると、その後の兄弟関係は断絶します。
経験上、間違いないです。
相続税額が増える
もうひとつの理由として、相続税の納税額が増えるから。
一次相続の際には、配偶者のこれからの生活を守るために「配偶者税額軽減」というものを受けられます。
具体的には、配偶者が引き継ぐ財産が1億6千万円以下、または法定相続分よりも少ない場合は、相続税が無税になる、というものです。
一次相続の場合、大抵の方が配偶者へ遺産を集中させて相続をします。
しかし二次相続では、配偶者税額軽減の税制上の特典がありません。
なので、そこで初めて相続税と向き合うケースが多いからです。
生前にきちんと対策を検討すべき
そのようなトラブルを避けるためにはどうすればいいのか?
しっかりと将来を見据えた生前対策が必要です。
相続対策、特に二次相続対策には節税に関する情報が溢れています。
もちろんできることを行うのは、とても大切なことです。
しかし生前対策の基本は、
1 遺産分割対策
2 納税資金対策
3 節税対策
の順番で考えるべきだと、私は捉えています。
節税ありきで考えると、家族円満に笑顔で相続を終えることができないケースが多いからです。
一次相続が起きて家族で話し合いをする際に、親に相続してもらうことがベストなのか、あるいは二次相続の事を見据えて、子供たちへ相続する割合を増やしておくべきか。
その検討が必要です。
また「どうやら我が家は相続税がかかりそうだぞ」という心配がある方は、一度資産の棚卸しをして現状把握が必要です。
というのも、節税対策には時間を味方につける必要があるからです。
遺産の分け方によって、当然、相続税の納税額の負担割合も異なります。
引き継ぐ遺産の内容によっては換金ができなくて、納税ができない可能性もあります。
そのようになりそうなら、納税資金対策も考えなければなりません。
それには、生命保険の利用が有効です。
しかし年齢条件や健康状態の悪化によって、保険の新規加入引き受けができなくなることもあります。
その意味でも、早め早めの準備ができたらベストですね。
少しでも気にかかったら先延ばしをせずに、思い切って一歩踏み出しましょう。
それがトラブルを未然に防ぐ第一歩になることでしょう。