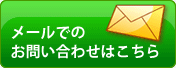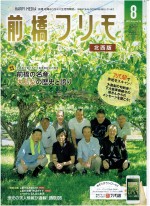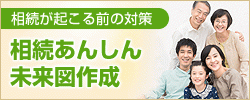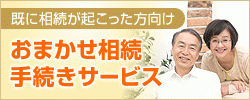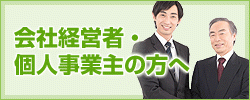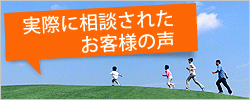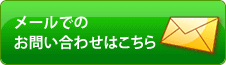大事な情報を伝えるのに最適なツール、エンディングノート
2009年のことになります。
いつも通り出社の準備をしていたある朝、母から携帯電話に連絡がありました。
「お父さんが病院へ運ばれた」
父は病気を患っていたので老人介護施設にお世話になっていたのですが、いつものように施設のスタッフに介助をしてもらいながら朝食を摂っていたところで容体が急変したというのです。
会社へ出社できない旨の連絡を済ませ、すぐに病院へ向かいました。
そこで医師から言われたのは、
「今夜を越せるか分かりません。集まれるご家族に連絡をして下さい。」
と。
あまりに急なことで、簡単に気持ちの切り替えができませんでした。
いつかは別れる日が訪れると理屈では分かっていても、それが今日なんだという事実をなかなか受け入れられなかったのです。
しかし、だんだんと息遣いが細くなっていく父を何時間も看ていると、次第に受け入れられるようになっていきました。
そしてそのように冷静な気持ちになってくると、これから私がすべきことをイメージするようになりました。
病院への支払い、葬儀の準備、僧侶の手配など。
それには諸々まとまった費用が掛かります。
お金が下せなくなると支払いに困るので、病院近くの銀行ATMへ行き、当面必要な額としてキャッシュカードで一日の出金限度額50万円を引き出しました。
いま振り返るとそんなバタバタと慌てる必要もなかったとも思いますが、これから先が不安になってしまい起こした行動でした。
銀行口座が使えなくなる
金融機関は死亡の事実を知ったとき、すぐに口座の凍結をします。
凍結とは、口座からの出金や入金ができなくなる、ということです。
まあ、入金する人はいないでしょうけどね。
なぜ金融機関がそのようなことをするかというと、相続手続きのために預金残高の増減を防ぐ、という目的もありますが、
相続財産を誰かれ構わず引き出されて、銀行がトラブルに巻き込まれてしまうことを避けるためです。
口座名義人の相続人が窓口に訪れて声を荒げ、
「おい!なんであいつに出金をさせたんだ!」
「遺産分割ができなくなってしまったぞ!どうしてくれるんだ!」
なんて苦情がきたら対応に困りますもんね。
銀行に情報が届いたときから凍結される
以前、お客様から「役所に死亡届けを出すと、銀行のお金が下せなくなるんだよね?」と聞かれたことがありました。
どうやら、役所は死亡した事実を金融機関へ情報提供するものだと誤認していたようです。
そんなことは致しません。
また、出来るわけないです。
亡くなった人がどこに口座を持っていたかなんて、役所は知る由もないですから。
金融機関は、家族からその事実を知らされたときに凍結をします。
あるいは新聞のお悔やみ欄を金融機関の担当者が見て、訃報の事実を知り得たときにも凍結されます。
勝手に使うと大変なことに
ですから家族がその知らせを行わないと、場合によっては普通にお金が下せることもあります。
しかし、むやみやたらに出金することはお勧めしません。
まず第一に、遺産分割を相続人(引き継ぐ人)間で話し合う際にトラブルの素になります。
使い込みを疑われるかもしれないですよ。
そして、相続放棄ができなくなる可能性もあります。
裁判所にその申請を否認される、ということです。
相続放棄という手段はマイナス財産の方が大きい場合に選択することが多いのですが、当然その先には債権者(お金を貸している人)がいます。
その人たちからすれば、貸したお金が棒引きにされては困ります。
わずかでも回収したい気持ちは当然のことですよね。
裁判所は公平な判断をします。
葬儀費用、治療費、仏具購入費の支払いが目的で、あまり高額でなければ大丈夫かも知れませんが、「身内のお金なんだからいいだろう」などと軽く考えるととても危険です。
わずかな金額を使い込むことによって、数千万円や数億円の借金を被らなければいけない。
とてもリスキーだと思いませんか?
民法改正で使いやすく
これまでは口座が凍結されてしまったせいで、葬儀にかかる多額の支払いや生活費など、残された家族の負担が大きくて困る、といった問題がありました。
その問題を解消するために、2019年に民法改正が行われ、遺産分割前に預貯金の一部引き出しが可能になりました。
いくらまでかというと、
相続人1人あたりが引き出せる額=相続開始時の預貯金残高×1/3×法定相続分
(ただし金融機関ごとに150万円が上限)
です。
たとえば相続人(引き継ぐ人)が母・長男の2人として、預貯金が1500万円だった場合。
1500万円 × 1/3 × 1/2 = 250万円
250万円 > 150万円
したがって、150万円となります。
これで当面の費用は賄えるかもしれないですね。
口座のありかを調べるには
相続が発生したのだが、故人がどこの金融機関に口座を持っているのか分からない。
そんなこともよくあります。
では、どうすればいいのか?
それは地道に金融機関を回って調べるしかありません。
同一銀行の支店間は調査可能ですが、他銀行はつながりがありませんので。
自宅に届いた郵便物や、タオルやカレンダーなどのノベルティをヒントにして地道に探していきましょう。
エンディングノートは宝探しの地図
故人がどこに何を持っていたのか。
簡単に明らかにできる方法があります。
エンディングノートを書き残すことです。
最近は終活ブームなので、もしかしたらどこかで耳にしたことがあるかも知れません。
これは非常に有効な方法なので、是非とも書いて欲しいです。
遺書ではないのですから、深刻に考えるのではなくどうぞ気軽な気持ちで書き始めてください。
口座を開いている金融機関と暗証番号、ネットバンクがあればログインするためのパスワードやメールアドレス、銀行届出印の印影と保管場所。
私のお客様で、どこを探しても見つからなかった故人の実印と銀行届出印と通帳が、冷凍庫の中にあるバターの缶からキンキンに冷えた状態で後日見つかった、と聞いたことがあります。
エンディングノートは家族へのラブレター
エンディングノートは保有する金融機関情報を伝える以外にも、いろんなことができます。
今までの生い立ちと思い出、家族への想いや感謝の気持ち、連絡をして欲しい友人の連絡先、葬儀のやり方、遺した財産の分け方やその使い方、なぜそのように考えたのか、など。
口では言いにくいけど、文字でなら伝えやすいことってありますよね。
また手書きの文字の温かみがあって、気持ちがより伝わりやすいと思います。
印刷された味気ない年賀状より、手書きの年賀状の方が、字の上手下手は関係なくもらってうれしいものですよね?
恥ずかしがらず、素直に気持ちを表してみましょう。
なお、かなりの機密情報が記載されていますから、エンディングノートは厳重に管理をしてくださいね。
厳重すぎて見つからない、のでは意味がありませんが。
私は、生命保険証券を入れたケースと共に保管することをお勧めしています。
いつか必ず、家族はそれを開くことになるからです。
私はお客様と一緒にエンディングノートを書くサポートもしております。
興味がある方は、どうぞお問い合わせください。