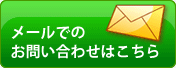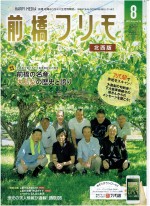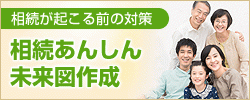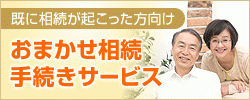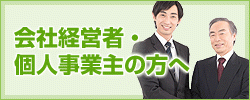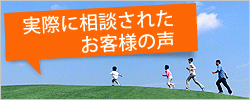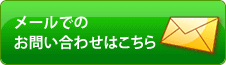相続に強い士業を見つけるための最短ルート
以前、パソコンを買い替えようと近所のパソコンショップへ行った時のこと。
この際WindowsからMacに替えてみようかな?とも思っていたので、近くにいた店員に質問をしました。
どんな選び方をすればよいのか、と。
ちなみに私はパソコンにまったく詳しくありません。
パソコンって、なんでこんなにたくさんカタカナの専門用語があるんだろ?
もっと分かりやすい日本語に訳してくれればいいのに。
と昔から思っています。
説明をしてくれた店員は、どうやらパソコンのことがとっても大好きな様子。
私のニーズなどお構いなしに、スペックや機能について流ちょうに説明をしてくれます。
まるで説明をする自分に酔いしれるかのように。
次第に私の視線は焦点がぼんやりとしてきて、店員の説明が言葉ではなく音としか認識をしなくなっていきました。
「早くここから私を解放してくれないかな」
もう頭の中はそれでいっぱいです。
私の小さな目をさらに細くしてぼーっとしていたら、ようやく説明をやめてくれました。
もちろん購入などせずに店を去りました。
でも反面教師としてよい学びになったので、ある意味で有意義な時間にもなりました。
難しい言葉を使いたくなりがちに
ある事柄に精通していると、詳しいがゆえに難しい言葉を使いがちになります。
生命保険営業マンとして活動をしていた時にいつも気を付けていました。
お客様は生命保険の素人です。
保険金と保険料の違いも分かりません。
経験を重ねると自ずと知識も高まるので、余計に難しい言葉を使ってしまいそうになります。
でも相手は、ほぼもれなく保険の素人。
気を付けないと、遠い目になって耳を閉じていきます。
小学生にも分かるような言葉で伝える意識をもって日々臨んでいました。
いまでもその意識は変わっていません。
専門家が陥りがちなこと
私は知識向上と最新の実務情報を得るために、様々な研修や勉強会に参加をしています。
とても役に立つものもあれば、これはひどいなと思うものもあります。
しかし後者の場合でも、学ぶことは結構あります。
「どうしてダメだと思わせてしまうんだろう?」
と研究ができるからです。
もっとこうしたらいいのに、と思うことのひとつに「難しい専門用語が多すぎる」というのがあります。
弁護士の話は特にその傾向が強いように感じます。
もちろん聴衆が素人ではないという前提でお話をしてくれているからなのでしょうが。
法律の専門家が常識だと思っている知識レベルは、私を含めた一般人にはかなりハイレベルと感じるものもあります。
知識の差を埋める通訳の必要性
以前に私は、仲介役としてお客様と弁護士と同席をしたことがあります。
そして実際に聞いた、法律事務所を出てからのお客様のひと言。
「難しくていつも何を言ってるんだかよく分かりません。」
驚きました。
すでに何十万円も支払っているのに。
結局その案件が終わるまで、事前に私とお客様の間で質問事項を打ち合わせしておいて、弁護士の説明にお客様が腑に落ちていない場合は私が深掘りをしてさらに聴く、というスタイルにしました。
そのおかげで、互いの意思疎通がスムーズにできるようになりました。
もしかしたら弁護士の方からしても、好都合だったかも知れません。
法律のプロと素人の知識の差を埋める役回りが通訳としているわけですから。
税金の話だって難しい
税金の話もそうです。
一般的には税金の話は難しいです。
きっと多くの人に馴染みのある税金といえば、消費税くらいでしょう。
毎月給料から天引きされる所得税や住民税だって、経理の仕事をしている人でもない限り、きちんと理解できている人は稀だと思います。
ですから相続税やら贈与税など、まったく身近ではない税金については仕組みすら分からないのも当たり前ですよね。
できるだけ難しい話にならないように、必要がなければ過度な説明は避けるようにしています。
困惑させてしまうだけなので。
情報を与えすぎない
相続には民法や税法の話が密接に関わっています。
ですからそこを避けては通れないのですが、誤解を恐れずに言えば、必要のないところは避けて通ってもいいのではないか?と思っています。
それは、お客様が求めていない知識を必要以上に提供しない、という意味です。
そのためにはしっかりとしたヒアリングをすることが絶対条件です。
また、きちんと聴かせて頂く前からあれやこれやと情報を提供してしまうのも、お客様の頭の中は混乱するばかりです。
必要な情報だけ厳選して提供することがプロだと思います。
無責任な言い方ですが、私は法律や税金の深い知識について、弁護士や司法書士や税理士にまったくかないません。
しかしそれぞれの立ち位置ごとに、果たすべき役割があると思っています。
私の果たすべき役割
例えれば一軒の家を建てるとき、
設計士、基礎工事、大工、内外装工事、電気工事、インテリアコーディネーターなど、様々な専門職が携わります。
もちろん各職人たちの技術力も仕上がりの良し悪しを大きく左右させますが、その工程管理や施主の意向をきちんと職人へ伝える現場監督がいないと、満足のいく仕上がりにはならないです。
しかも各職人には得手不得手があります。
施主が望む理想を叶えるには、業者選びも監督の腕の見せ所でしょう。
私の果たすべき役割は、相続の現場監督です。
お客様の置かれている状況や心配事と、こうしたい!という夢や想いをしっかりと聞き出すこと。
そしてそれを実現するための、相続について精通していて、お客様のメリットを最大限に考えてくれるプロフェッショナルを探し出すこと。
そして上手にコーディネートして差し上げること。
だと考え、日々活動をしています。
「お客様が望む結果を手に入れるための最短ルートになる」と自負していますので、まずはご相談を下さい。