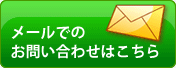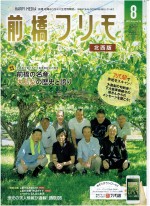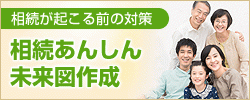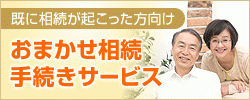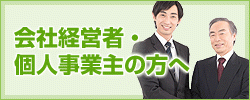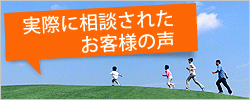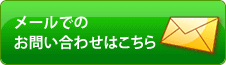子供がいない家庭の相続における3つの問題点
先日、スーパーで買い物をしていた時のこと。
おばさま二人が眉間にしわを寄せて、深刻そうな話をしています。
どうやら相続についてのお話。
よくないとは思いつつ、職業柄ちょっと気にかかって、つい聞き耳を立ててしまいました。
「遺産」とか「遺言書」などのキーワードが聞こえてきます。
会話の輪に入っているわけではないので、詳しくは聞こえません。
しかし、よーく聞いてみると・・・
・・・
どうやら、ワイドショーで話題となった紀州方面の資産家の方についての話でした。
・・・我が事でもないのに、あんな真剣に話し合いができるんだぁ…と感心をしてしまいました。
他人のスキャンダルはおもしろいものなんでしょうね。
遺言書が見つかり事態が急変
あの紀州の資産家の方は、とても年齢差がある奥様ひとりを残して亡くなってしまいました。
それはもうしばらく前の出来事だったのですが、最近、遺言書が見つかったことによって再びワイドショーで取り上げられたのです。
それなのでスーパーで見かけたおばさま方は、眉間にしわを寄せながら、あのご家庭の事について真剣に心配を?していたのでしょう。
遺産をもらえる権利が消滅
話題となったあの方には、お子様がいらっしゃらなかったそうです。
ですから法律上の相続人は、奥様。
そして、複数いらっしゃる兄弟姉妹。
この方々で遺産を分け合うことになります。
しかし、
「個人の全財産を、自治体へ寄付をする」
という趣旨の遺言書が出てきてしまったので大変です。
奥様は遺留分請求といって遺言書で指定された相手に対し、その半分を請求する権利がありますが、ほかのコラムでも述べましたように兄弟姉妹にはその権利はありません。
※遺留分(いりゅうぶん)とは、最低限の遺産の取り分のことです
遺言書さえなければ故人の奥様と遺産分けができたのに、これでは兄弟姉妹の取り分はゼロです。
そのためなのか、そんな遺言書は無効だ!と兄弟姉妹ら遺族の方々から遺言書の無効申し立てを行ったそうです。
これについての私的なコメントは致しませんが、相続コンサルタントの立場として、このような家族構成の相続について注意点を示したいと思います。
懸念される注意点
故人に子供や親がいない場合、遺産を分け合う相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。
ここで懸念される注意点は以下の通りです。
- 遺産の内容を、兄弟姉妹に対しすべて公開しなければならない
- 遺産のほとんどが不動産の場合、遺産分けのための金銭が必要になる
- 名義変更や銀行の解約など、すべてのことに兄弟姉妹を含めた相続人全員の実印が必要になる
義兄弟姉妹に全資産を公開
夫婦で築いてきた財産を義理の兄弟姉妹に、すべて公開しなければなりません。
法律上の相続人ですから仕方ありません。
義兄弟との関係性がよければいいですが、あまり関係性がよくない相手に自分の財産をつまびらかに教えなければならないのは、心情的に避けたいものですよね。
守りたい財産のために金銭が必要
群馬県のように地価の安い地方都市ではあまりありませんが、首都圏で持ち家があると、遺産総額のほとんどの割合を土地家屋が占めてしまうことはよくある話です。
配偶者はそこに住み続けたいものの、他の相続人から法定相続分の金額を請求されて、それを支払う金銭がない場合は、家を売らなければならなくなります。
高齢の単身者が、賃貸アパートを借りることはとても大変です。
簡単には貸してもらえないケースも多いですから。
手続きがいつまでも進まない
そして各種変更や解約には、相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書が必要です。
兄弟姉妹の全員が健在ならまだいいですが、亡くなっている場合は代襲相続(だいしゅうそうぞく)といって、その子供(甥や姪)が相続人となります。
相続人全員が近くに住んでいて、かつ話し合いがスムーズにできればいいですが、遠方や海外に住んでいたり、入院中や認知症を患っていたりだと、書類集めや意志疎通が滞って相続手続きが全く進まないこともあります。
解決策は遺言書
そのような事態を避けるためには、きちんと遺言書を残すことです。
「配偶者にすべての財産を相続する」
という趣旨の遺言書があれば、前述の通り兄弟姉妹には遺留分がないので、すべて配偶者が遺産を受け取れるようになります。
そうすれば各種変更手続きや銀行の解約も、配偶者ひとりだけで手続きができます。
相続税が発生しそうなケースでも、たくさんの相続人たちと相談する手間や時間もなくなり、スムーズに前進していけます。
もし兄弟姉妹に遺したい財産があるなら、それも遺言書に盛り込むとよいでしょう。
しかしその場合にも、配偶者の遺留分(法定相続分の半分)を超えないように注意しましょう。
そうでないと、遺産相続トラブルに発展してしまうかもしれません。
行先指定をしたい財産は家族信託という方法も
Aさんは、先祖代々受け継いできた土地に住んでいたとします。
そしてAさんが亡くなり、その土地は奥様が相続したとします。
では奥様が亡くなったら、その土地は誰に相続されるのでしょう?
子供がいない場合は、奥様の兄弟姉妹へ相続されます。
Aさんの兄弟姉妹からすれば、
「我が血族が先祖代々受け継いできた土地が、別の血族の持ち物になってしまうのは納得いかない・・・」
という思いがあることでしょう。
しかし、
「A自身が亡くなったら土地は配偶者に相続する、そして配偶者が亡くなったらAの兄弟姉妹に相続する」
という遺言を書いたとしても、それは効果がありません。
なぜなら遺言書での財産の行先指定は、Aさんの相続人までしかできないからです。
遺言書はあくまで自分の財産の処分方法について指定ができるものであって、その次の持ち主の処分方法までは口を挟めません。
この例のように次の次まで財産の行き先を指定する場合には、家族信託(かぞくしんたく)を活用することもひとつの方法です。
家族信託とは、その言葉の通り「信じる家族に自身の財産を託す」という、財産の管理と行き先を指定する契約を結ぶ事です。
亡くなったあとの事を指定することももちろん可能ですが、自身が認知症となって財産管理ができなくなってしまう前に、その管理指定ができることにとてもメリットがあります。
家族信託は主に司法書士が扱っていますが、これについてすべての司法書士が精通しているわけではないので、飛び込みで司法書士事務所に行ってもお互いによく分からない不毛な時間を過ごすことも考えられます。
弊社にはそれに詳しい司法書士とのつながりもありますので、関心がある場合はお声掛けください。
配偶者のために遺言書を
子供がいないケースでの相続は、トラブルに発展する可能性が高いです。
なぜなら、生活を共に過ごしたことのない親族と金銭価値あるものを分け合わねばならないからです。
子供がいない、また親もいない方は必ず遺言書を書くべきだと私は思います。
それが家族への思いやりです。
遺言書、そして家族信託契約ともに、自分の意思表示ができるまでというタイムリミットがあります。
認知症が発症した時点で、それらはできなくなってしまいます。
懸念があるとお感じの方は、どうぞご相談を下さい。