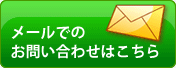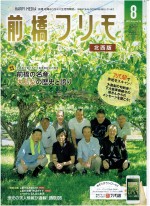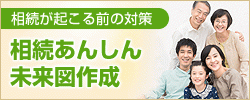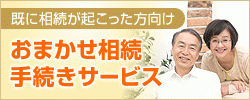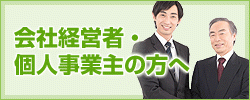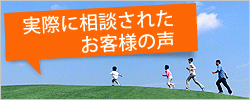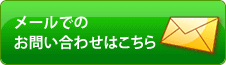独身者が必ずすべき相続の事前準備
先日お客様のお宅で、生まれたばかりの赤ちゃんと会ってきました。
丸々としていて、とても可愛らしかったです。
初めて対面をする私を見て、ニコニコと笑顔。
・・・かわいい。
加齢のせいでしょうか、赤ちゃんの些細な動きひとつ見ても涙腺が潤んでしまいます。
その夜、いつも通りの我が家の食卓。
目の前には、中学生の我が子たち。
彼らもいつか結婚をして子を授かり、私も自分の事を「じぃじ」などと呼び、孫と触れ合う日が訪れるのかな?などと、ひとりで勝手に想像をしてしまいました。
と同時に、そもそも彼らは結婚をするのかな?とも。
大人になったからといって、必ず結婚をして子を持つとは限りません。
ライフスタイルが多様化している今、その可能性は未知数です。
二種類の独身
独身と言っても二種類あります。
「生涯ずっと独身」と「今は独身」
では、独身者が亡くなったら誰が遺産を引き継ぐのでしょうか?
常にその権利がある配偶者はいません。
第一順位になるのは、子供。
「生涯ずっと独身」の人は、養子縁組でもしてない限り子供はいない。
はずです、一般的には。
しかし稀なケースですが、婚外子を認知していることもあります。
婚外子とは、結婚をしていない男女の間に生まれた子供のことです。
その場合には、その子供がすべてを相続します。
「今は独身」の人は、過去に結婚をしたことがある人ですね。
子供がいたものの離婚をして前妻が引き取った。
その場合も、相続人はただ一人。
前妻との間の子供だけです。
配偶者も子供もいない場合
この場合で相続を受けるのは親になります。
そして親がすでに他界をしていた場合は、その親である祖父母となります。
配偶者も子供も親もいない場合
この場合で相続を受けるのは、兄弟姉妹になります。
そして兄弟姉妹の中で、すでに亡くなっているが子供がいる場合は代襲相続(だいしゅうそうぞく)といって、その甥や姪が相続人となります。
親族が誰もいない場合
では子供も親も兄弟姉妹もいない場合は、財産はどうなるのでしょうか?
答えは、すべて国のものになります。
しかし、夫婦関係と同等の生活をしていた内縁関係や事実上の養子と認められる人や、報酬を得ずに看護や介護を行っていた人は、特別縁故者といって相続を受ける権利が発生するかもしれません。
これは自然と指名されるわけではなく、家庭裁判所へその旨の申し立てをする必要があるます。
何もしなければ繰り返しですが、すべてが国のものになります。
該当する可能性がある方がいる場合は、期限内に申し立てをする行動をとりましょう。
特定の人に遺したいなら
特定の人に財産を遺したい。
そのような想いがあるなら、事前の対策が必ず必要です。
いくつか方法は考えられますが、
ひとつは養子縁組をするという方法。
これで法律上の相続人となるので、その人にすべての遺産を遺せます。
養子となる人の年齢は何歳でも構いません。
手続きの窓口は各市町村役場で行えます。
また別の方法として、特定の人に遺すという趣旨の遺言書を書く、というのもあります。
相続は「自分の財産を自由に処分が可能」が原則なので、好きな人に遺せます。
別に親族や姻族じゃなくてもOKです。
生前お世話になった人、お世話になった施設や団体、長年住み慣れた自治体など。
想いの言葉を一言添えてしたためるといいですね。
しかし遺言書が発見されず、その想いが伝わらないのでは意味がありません。
自筆遺言ではなく、公証役場で公正証書遺言を作るとよいでしょう。
何がどこに・・・を防ぐには
独身者の相続で最大の課題は、
どこに何をどれだけ持っているかについて知っている人がいないこと。
お金を預けている金融機関や証券会社、保有する不動産。
または借金などがあれば、その借入先など。
最近はネット銀行や保有資産情報をインターネットでの管理が普及していて、紙媒体で残っていないものが増えています。
実印や銀行印、各種パスワードなど誰も分からなくて、相続手続きが一向に進まないケースがよくあります。
それを防ぐには、エンディングノートが最適です。
そこに資産管理一覧表を記入します。
常に最新版になっていなくてもOKです。
暗証番号やネットで管理しているもののパスワード、大切なものはどこに保管してあるか。
そして、特定の人へ遺す場合はその想いを伝えるメッセージを添えられたらベストですね。
大切な情報が詰まったノートですので、くれぐれも管理は気を付けてくださいね。
独身の方からのご相談も喜んでお受けしますので、まずはお気軽にご相談を下さい。