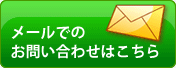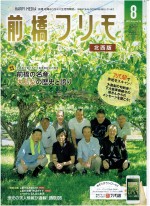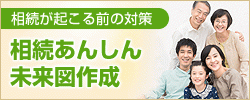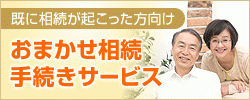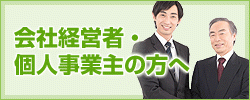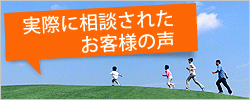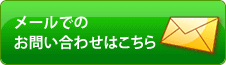他人事ではない、空き家問題
いまの住まいを建てる前まで、私は空き家となっていた妻の実家で暮らしていました。
築40年ほどの戸建ての家でしたが、子供が生まれ賃貸アパートでは手狭になっていたので子育てにとても助かりました。
近所に住む方々のほとんどは、子育てを終えた年配のご夫婦あるいは単身者のご家庭。
先日しばらくぶりに以前の住所へ行ってみたら、そのご近所が空き家だらけになっていました。
この数年間でお亡くなりになったり、介護施設に入居した方が多くいたそうです。
その空き家の何軒かには、割れた窓ガラスを修復した跡がありました。
空き巣が入って、それを直した跡とのこと。
かく言う私が以前住んでいた家も、我々家族が退去後は空き家となって、ある日警察から「不審者が出入りしている」との連絡がありました。
そのまま不審者が住み着いたら困るし、うっかり火でも出されたら近所に迷惑をかけてしまう、ということで、家族会議を重ねた末に家を取り壊しました。
住み手を失った家の管理は大変です。
ますます増えていく空き家
平成30年の住宅・土地統計調査によると、空き家率の全国平均が13.5%なのに対し、群馬県は16.6%。
全国で9番目に多いです。
空き家のうち約4割は賃貸用でも売却用でもなく、誰も寝泊まりをすることがない廃屋で、管理不十分住宅なんだそうです。
戸数にして、62,200戸。
この数字は前回の調査よりも増えており、これからも増加傾向が続きます。
あなたのご家庭にも、このようになりそうな物件はありませんか?
考えるべき、家の仕舞い方
暮らしのグローバル化や核家族化がいっそう進み、実家を巣立っていった子供たちは、それぞれ新しい住居を持つことが普通になっています。
もはや育った実家を代々受け継いでいく、という考え方は馴染まないのかも知れません。
家の仕舞い方、についてもきちんと考えなければいけない時代になってきました。
なぜなら資産であると考えられてきた家が、負の資産になってしまうからです。
人が住んでいない家の老朽化は、加速度的に進んでいきます。
それを管理する人の負担は計り知れません。
雑草むしりや植木の手入れ、不法ゴミを投棄させない、空き巣や放火を防ぐ見張りなど。
管理する人が近場に住んでいればまだいいのですが、県外や外国に住んでいたら、日常的にその手間をかけることはとても難しいですよね。
誰が管理をするの?
親が亡くなり相続で家を引き継ぐことになった場合は、当然その人に管理義務が発生します。
では相続放棄をした場合、その家の管理は誰がするのでしょう?
例えば、
家の持ち主である親が亡くなった。
財産を調べたら借金がたくさんあって、保有する預貯金と家や土地の評価額を大きく上回っていた。
借金を被りたくないので、相続人である子供は相続放棄を選択。
無事に手続きを終えてホッとしたのも束の間、相続放棄したはずの家について近所から苦情が。
庭木が道路にはみ出て通行の妨げなっている、家の中の大量のゴミから悪臭がまき散らされている、放置され続けた家が倒壊してきて隣人が損害を被った、など。
このような場合、いったい誰が管理責任を問われるのでしょうか?
相続放棄をした後の財産の行方
相続人の全員が相続放棄をしたら、亡くなった人にお金を貸していた人(債権者)は泣き寝入りになってしまうのか?
それは違います。
債権者が家庭裁判所へ「相続財産管理人」の選任を申し立てると、一般的には弁護士が選任されて、保有していた資産を精算し債権者へ配当が行われます。
しかし、ここで問題が。
法律ではそのような制度があるものの、実務的にはなかなかそう簡単に事は運びません。
当然のことですが弁護士は仕事として相続財産管理人に就くのですから、家庭裁判所への申し立てには費用がかかります。
資産の内容によりますが、その費用およそ30~100万円。
それを上回る金額が回収できるのならいいですが、相続人が放棄をするくらいですから預貯金もない、土地も売れない、ということで債権者はお金をかけるのに見合わないので申し立てをしない、というケースも多いのです。
結果、泣き寝入りになってしまうわけですが。
するといつまでも経っても相続財産管理人が現れず、家の管理責任者がいないことになってしまうのです。
相続放棄しても管理責任は残る
話は戻りますが、先ほどのケースでは誰が管理責任を問われるのでしょうか?
答えは、相続人。
民法第940条第1項に、以下のように規定されています。
『相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。』
つまり、相続財産管理人が選任されるまでは、相続放棄をしていたとしても相続人が責任を負わなければいけない、というルールになっているのです。
そんなの納得できない!と言っても仕方がないのです。
司法統計によると、年間の相続放棄の申立件数は約20万件。
そういう法律にでもしないと、このようなご近所トラブルが絶えないからなのでしょうね。
空き家の管理に疲れ果てています
先日ご相談にお見えになった方のお話です。
「親が亡くなって、二人の兄弟で財産を分け合った。
預貯金のすべては兄が、私は実家を相続しました。
毎週末の休日といえば、夫婦そろって誰も住まない実家の掃除と雑草むしりに追われています。
まだ父が亡くなって1年も経っていませんが、もう本当に疲れ果ててしまいました。
処分するにも、あんな田舎では誰も買ってくれる人は現れません。
不動産屋もまるで興味を示してくれません。
どうすればよいのでしょうか?」
遺言書がなかったのなら、相続人全員の合意(この場合は兄)があれば遺産分割協議のやり直しもできるでしょうが、話し合いは容易いことではないでしょう。
どう考えても兄が相続した財産の方が魅力的なので、話し合いに応じてくれるかも分かりません。
すでに兄弟の関係性がギクシャクし始めている、ともおっしゃっていました。
お互いへの思いやりと譲り合いの気持ちが必要不可欠ですね。
知らないことによる不幸
このように、すでに終わってしまった後のご相談を聴かせて頂くたび、
「あぁ、もっと早く来てくれたら良かったのに…」
と思ってしまいます。
相続が起きる前だったら、もっといろんな助言ができるのに。
その助言に従い行動するかどうかは、お客様が決めればいいことです。
しかし必要としている知識がないと、知らないがゆえに何も行動ができません。
知識がないせいで不幸な相続を迎える人を少しでも減らしたい。
私は毎日そう考えています。