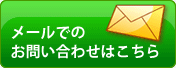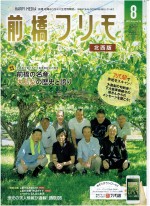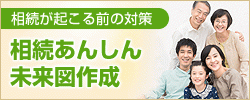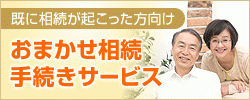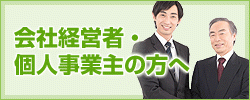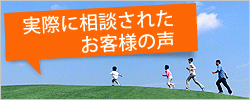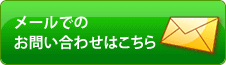あなたの法定相続人は誰ですか?
私が生命保険会社に勤めていたときの事です。
お客様のお宅で生命保険へ加入の申し込み手続きをして頂いている最中に、その保険金の受取人を誰にするかについてで、目の前で親子ゲンカが始まったことがあります。
そのお客様は60代後半の男性、二世帯住宅に同居する長女と、独身で一人暮らしの長男がいます。
生命保険の契約をする父親は保険金受取人を長男にしようとするのですが、近くでその話を聞いていた同居をしている長女が口を出してきました。
「普段お父さんとお母さんの世話をしているのはあたしなんだから、そこのところをちょっとは考えてくれてもいいんじゃないの?」
「お前は嫁に出ていったんだから、この家だけ残れば文句はないだろう?」
「あたしだって建て替えの時に頭金を出しているんだから、この家をあたしが継ぐのは当たり前でしょ!いつも買い物や病院の送迎とかあたしの時間を削ってやっているんだから、少しはそこを考えてよ!」
「長男はいずれ墓と〇〇姓を継いで守っていかなければいけないんだから、財産は長男が継ぐのが当たり前だろう!」
相続は長男が引き継ぐのが当然と考える父親と、相続は平等に分けるべきと考える長女の、価値観や考え方の相違が親子ゲンカの原因でした。
私が仲裁に入って、「保険金受取人の変更はいつでも何度でもできますから」とその場ではご長女に渋々とですが納得をしてもらい、なんとか契約手続きを済ませました。
その後、保険金受取人変更の依頼連絡はありませんでしたが…。
しかしどうして「長男が継ぐのが当たり前」という発想があるのでしょうか?
どうも相続制度の歴史によるものみたいですね。
制度の昔と今
その昔、相続は明治31年に旧民法で制定された「家督相続(かとくそうぞく)」という制度に従って行われていました。
これは戸主が持つその地位や権利などのすべてを長男に継ぐ、というものでした。
妻や子どもが何人いたとしても、です。
身分制度が厳格だった明治以前は、その家で営む事業(家業)を継ぐということが家長としての責任だったのでしょう。
しかし家制度や職業観などが時代に合わなくなってきて、昭和22年の民法改正で廃止となり「法定相続制度」が導入されました。
法律で決められた順番に基づいて相続をする制度です。
これにより、配偶者や長男以外の子供も相続権を与えられました。
しかしそれから約70年が経ったいまでも、「相続は長男が継ぐもの」といった考え方がまだまだそこら中にはびこっています。
いまの高齢者の親たちは家督相続を経験してきました。
ですから、それを見てきた高齢者世代がそのように考えるのは無理もないことかも知れません。
しかしいまの現役世代とでは、とても大きな世代間ギャップがありますね。
相続を受ける優先順位
現在の制度では、誰かが亡くなったらその人の相続人が法定相続順位に従って、決められた割合で分けるように定められています。
少しややこしいですかね。
相続人とは、亡くなった人の財産を引き継ぐ人のことです。
そして法定相続順位というのは、民法で定められた、相続を受ける権利の優先順位のことです。
順番が決まっていないと、血のつながりのある人がみんな一斉に群がってきそうですものね。
そんなことが起きては困ります。
ですから民法では、「ここからここまで」という範囲と順番を設けています。
そして故人との関係の近さによって配分の割合は異なり、法定相続割合は以下のようになります。
|
配偶者 |
子 |
親 |
兄弟 |
|
1/2 |
1/2 |
|
|
|
2/3 |
|
1/3 |
|
|
3/4 |
|
|
1/4 |
配偶者は必ず相続人
まず第一に、配偶者は常に相続の権利があります。
必ずです。
ですから、入籍していたら必ず相続権があります。
入籍の翌日でも、です。
逆にどんなに長く一緒に暮らしていても、内縁状態では一切相続権はありません。
何十年も連れ添ってきて、周囲も認めるほど、まるで夫婦のような関係だったとしてもです。
戸籍への記載があるかどうか、これに尽きます。
法律に、同情や感情が入る余地はありません。
子供と分ける場合
そして配偶者は、自分以外にも相続人がいる場合は遺産を独り占めにすることができず、その誰かと分け合わなければいけません。
故人に子供がいる場合、そこと分配をします。
どれくらいの法定割合かと言うと、半分ずつ。
例えば、故人のすべての財産を洗い出したら、ちょうど6000万円だったとしましょう。
その場合、配偶者が3000万円、子供が3000万円(子供が複数いる場合はこれを案分します)という分け方になります。
自分との子はもちろんですが、故人とは再婚で、別れた前妻との間に子供がいる場合は、その子とも分配をしなければなりません。
自分との間の子ではありませんが、「亡くなった人の子」ですから相続人になります。
もしも前妻の子が未成年だった場合は、その子の親権者と財産の分配の話し合いをしなければいけません。
その場合の親権者は前妻のケースが多いので、トラブルが懸念されます。
赤の他人と、金銭の取り分についての話をするのですから。
複雑な人間関係でトラブルが予想される場合は、事前に対策が必要です。
遺言書を書いて財産の分け方を決めておく、生命保険に加入して保険金で分配金を支払えるよう準備しておく、すでに加入済み生命保険の保険金受取人を検討する、生前に一部の財産を贈与するなど。
100の家庭があれば100通りの対策方法があるので、この限りではありませんが。
義父母と分ける場合
故人に子供がいなかった場合、次の法定順位となるのは故人の親となるので、義父母と分配することになります。
法定割合は配偶者が3分の2で、親が3分の1です。
先ほどの例でいうと、配偶者が4000万円で親が2000万円となります。
ちなみに、義父母はすでに他界しているが義祖父母がいる場合、そこと分けることになります。
親からすれば、我が子が亡くなってお金を分けてもらう、なんてまったく嬉しいことではないでしょう。
しかし我が子が築いてきた財産や、親が事前に譲ってあげた財産が、婿や嫁にそっくり取られてしまうのは許せない!という感情を持つ親御さんもいることでしょう。
ましてや嫁姑問題があるような、あまり関係がよろしくない義父母とのお金の話し合いは、トラブルの臭いしかしません。
義理の親に対してお金の分配の話、言いたいこと言えます?
子供がいないご家庭は、人一倍、事前の対策が必要です。
いろんなことを想定しておきましょう。
兄弟姉妹と分ける場合
故人には両親も祖父母も子供もいない。
では配偶者は次に誰と分配をするかと言うと、故人の兄弟姉妹です。
「自分の結婚式や親族の冠婚葬祭でちょっと会ったことがあるかな?」
という人たちとも、金銭の分け方について話し合いをしなければなりません。
法定割合は配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
先ほどの例だと、配偶者が4500万円で兄弟姉妹が1500万円。
故人と経済的な関係が近い配偶者の取り分が多くなりますが、その財産を故人と共に築いてきたのだから当然ですよね。
むしろ、財産形成に何の関係もない兄弟姉妹となぜ分け合わなければいけないの?
とも思ってしまいますよね。
でも、そういうルールなんです。
しかも兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、そこに子供がいる場合。甥や姪ですね。
その場合は、甥や姪が分配の対象となります。
もしかしたら、遠い親族と感じる人がいるかも知れません。
しかし、対象となる相続人の全員から書類に実印を押してもらえないと、遺産分割は終わりません。
金融機関の解約や名義変更や登記がいつまでもできないのです。
トラブルは感情によって引き起こされる
以前のコラムでも書きましたが、金銭の分け前の話し合いは、なかなか一筋縄にはいきません。
相続トラブルは法律で定められた論理ではなく、個人間の感情のもつれによって起きるものです。
ひとそれぞれ価値観や考え方が違う以上、どこに火種がくすぶっているか分かりません。
炎上を避けるには、相続人との間でいかに納得をしてもらい、わだかまりを小さくするための努力が大切です。
そのためには時間を味方につける必要があります。
早目に準備を始め、事前の対策を考えるべきです。
あなたの法定相続人はいったい誰なのか?
これが分からないと話になりません。
まずはそれを明らかにしたうえで、様々なケースをシミュレーションしてみましょう。
ややこしくてよく分からない、と思われる方はどうぞご相談を下さい。